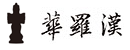出雲石勾玉 古墳時代
弥生土器
古墳時代の勾玉 出雲石と瑪瑙
縄文時代の勾玉

L27mm
W20mm
D7mm
孔直径4~8mm
縄文時代の勾玉です。
小振りですが、独特な存在感があります。
形の異様さは縄文時代の特徴の一つで見所です。
縄文時代後期頃には作り始められていたそうです。
縄文勾玉は、多様な形が存在します。
こちらのものは内側の弧の部分が “ く ” の字に見えるタイプです。
すり鉢状の孔の形も独特です。
片側の写真のみの掲載ですが、
同じような孔が反対側からも穿孔されています。
貫通部の径も大きめですが、大珠の孔とも異なります。
工具の違いがあるのかもしれません。
緑色に見える所もありますが、
良く見ると表面のちいさなくぼみに、
水晶のような細かい結晶があります。
ヒスイではなさそうです。
縄文時代には様々な石が石製装飾品に使われておりました。
この縄文時代の存在感を実物でご覧いただきたいと思います。
お問い合わせお待ちしております。
メールフォームは こちらです
2020.03.22